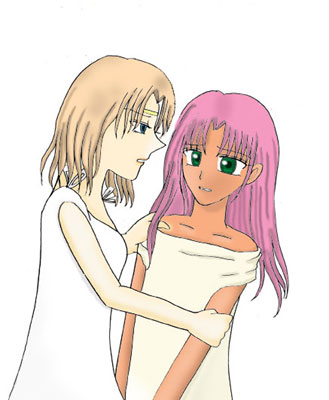 |
画像をクリックすると新しいウィンドウで元のイラストを表示します。(約43KB) Illustration: 麻生朋希 |
愛の淵 6 |
| シーラはその日の仕事が終わっても、王座に残っていた。緑色の便箋が、視界の端にわずかに映っている。 一日中ここで見張っていれば、かならず、手紙を持って来る者が居るはずだ。 我ながら、情けないと思う。 あのような手紙に脅かされ、王自らが、犯人探しを行っている。信用できる者が居ないのだ。 暫くして、誰かが入ってきた。 「王様、何をなさっているのですか」 それは、親愛なる神の一人、フィールだった。小さい頃からシーラのことを知っている。 「お前か」 シーラは言った。 瞳は相手を見ることなく、宙を彷徨う。見る必要はない。声を聞いただけで分かる。 信用できる者は居ないが、もしどうしても一人と言われれば、彼女を指名するだろうと、それくらい思っていた相手だった。 「わたしの首を出せば、あの悪魔共を止めることができるのか?」 相手は答えない。 「動の国も、静の国も、平和になるのか?」 構わずシーラは続けた。 「やはり、信じられない。わたしの首になんの価値がある? 王とは言え、先代の王の血は欠片も受け継いでいない。」 「王であることに、意味があるのでしょう」 女が言った。 それは、自分が今までのことの犯人であると認めたのか、それとも単に王に進言しているだけなのか、シーラにはわからなかった。 「白き壁から湧き出す悪魔は、おそらく、大神の怒りの現われでしょう。いつまでもいつまでも、仲違いしたままの、二人の兄弟への怒り。ですから、それぞれの国の支配者である王の首を生贄として差し出せば、怒りが収まるということでしょう」 もっともだ、と思えた。 今の自分は、大神の怒りよりも、セピアの怒りの方が怖い。セピアに嫌われるのが怖い。 「ありがとう、フィール。それはお前の嘘かもしれないけれど、今はそれを信じるしかないようです」 翌日シーラは、民衆を城下に集め声を大きくして言った。 「この国の王の首を取ったものに、この国の至宝を渡しましょう」 民衆が色めき立つ。 王を殺せば、国の至宝が自分の物になる。 これほど簡単に、財産を手にする方法があるというのだろうか。 反逆ではない。何しろ、王自らがそれを許可したのだ。 城門が開き、民衆が城へ押し寄せた。 フィールは笑顔で一礼して、封筒を、差し出した。 「信じていただいて、光栄です。けれども、わたしはフィールではございません。フィールは随分前に、わたしと交代いたしました。わたしはずっとこの国を見ております。この国は、決してひとつになってはいけないのですよ、王様」 昨夜の態度とは違う、シーラを軽視したような言葉で、親愛なる神は言った。 自分の首に、何か冷たいものが巻きついている、そんな感覚がシーラを襲った。 「そのような恐ろしい形相で見なくても、大丈夫ですよ。白き壁からの使徒は、王の首さえあれば、来なくなるでしょう。彼らも怖かったのですよ。自分達の居場所がなくなるのがね」 親愛なる神が差し出した封筒を受け取る気にはなれなかった。 騙されたという気は全くしない。手紙の主が大神ではなかっただけで、王の首を出せば白き壁から沸き出る敵は消えうせる、それは確かなのだ。 自分が死んだ後は、姉がまた王になり、戦争を終わらせるだろう。 それでいいのだ。 姉は静の国へは行かない。セピアも姉の下に尋ねてくる。そんな日常が欲しかったのだ。 最初から、自分が居なければ良かっただけなのだ。 城では戦争が起こっている。敵は自らの国の、民衆。彼らの意思で――民衆の意思は王の意思――、自分はここで殺される。 戦争は終わる。姉はここに残る。セピアも居る。 その三言だけが、何度も繰り返し、声にならない言葉となって、シーラの胸を暖める。 「シーラ!」 扉を開け、名の無い神が駆け込んできた。 「セピアから聞きました。至宝なぞはどうでも構いませんが、なぜ自ら命を落とすようなことを言ったの?死んでも構わないの?」 シーラは、頷いた。口は堅く閉ざしたまま。 その目に、覚悟を見て取って、名の無い神は自分にできることがないのでは、と不安に思う。 それでも、ただ一つ、言わねばならない事があった。 「シーラ、セピアは泣いていました。こどものように、ずっと泣いていたのです」 |
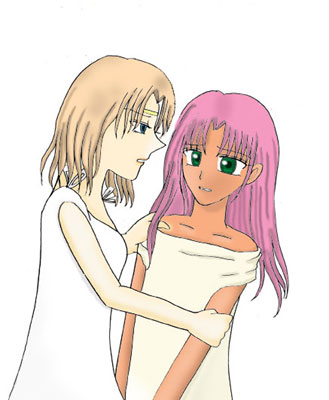 |
画像をクリックすると新しいウィンドウで元のイラストを表示します。(約43KB) Illustration: 麻生朋希 |
|
堅く閉ざされていた口が、僅かに緩む。何か言おうとして、言葉にならなかった。 End |